音楽理論って、わかりづらいですよね?
僕は理論を身につけるまでにめちゃくちゃ時間かかりました。
でも理論を覚えてから、コピーの時間が短くなったり、
セッションにも参加できるレベルに成長できました。
ただ、音楽理論関係の情報は、
教科書みたいな解説ばかりで本当にわかりづらいし遠回りすぎる。
当時の僕みたいに、
「ドレミファソラシドしか知らない人」でもわかるものや、
ベーシスト向けの情報が本当に少ないです。
そこで本記事では、
「これから音楽理論を勉強したいベーシスト」に向けて、
音楽理論の基礎となる「音名」をやさしく解説します。
この記事シリーズを読めば、
音楽知識ゼロの人でも簡単に理解できて、
すぐ演奏に使えるところまで到達できます。
- 英語音名に慣れよう
- チューニングでも英語音名を意識しよう
- 指板上で音の位置を見て・弾いてみよう
これを読んだ人が音楽理論を少しでも理解してくれたら嬉しいし、
もっとベースを楽しんでくれたら幸せです。
はじめに ベーシストに必要な音楽理論は全体の一部

音楽理論とは、
音楽を演奏・作成・説明するためのルール(体系)です。
音楽理論を学び、
演奏を感覚じゃなく頭で理解することで、
どんどん上達していきます。
とはいえ、全部を理解しなくてOK。
ベーシストは使うところだけ覚えれば大丈夫。
ベーシストが音楽理論を学ぶと、
- 周りの状況に合わせて演奏できるようになる
- 自分の演奏を俯瞰して分析できる
- ウォーキングベース等のベースラインを自分で作れる
- 初見曲やセッションでも対応できる
たくさんのメリットがあります。
このシリーズでは、
「音楽知識ゼロでもわかりやすく実践的に使える音楽理論」
をテーマに解説していきます。
音楽理論の基礎「英語音名」を覚えよう

記事を読んでる人の中には、
「ドレミファソラシドくらいしか知らない…」
って人もいると思います。
当時の僕も同じでした。
なので、同じスタート地点から進めていきます。
ただ、これから説明していく中で、
どうしても専門用語がちょこちょこ出てきます。
難しい言葉はできるだけ嚙み砕いて説明するので、
一緒に少しずつ学んでいきましょう!
まず第一歩として、
英語音名を覚えるところから始めましょう。
「ドレミファソラシド」を「C D E F G A B C」で覚えよう

音名というのは「音の名前」のことです。
学校で習った「ドレミファソラシド」
これが音名です。
でも音楽理論では、
音名をアルファベットで表します。
| ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ | ド |
| C | D | E | F | G | A | B | C |
「なんで?」って感じるかもしれませんが、
「そーいうものだ」と割り切ってください。
最初は難しいけど、繰り返し使えばすぐ慣れます。
これから先は「ドレミファソラシド」じゃなく、
「CDEFGABC」で呼ぶクセをつけていきましょう。
記事内では「CDEFGABC」で進めていくので、
一緒に少しずつ慣れていきましょう!
チューニングで「英語音名」を意識しよう
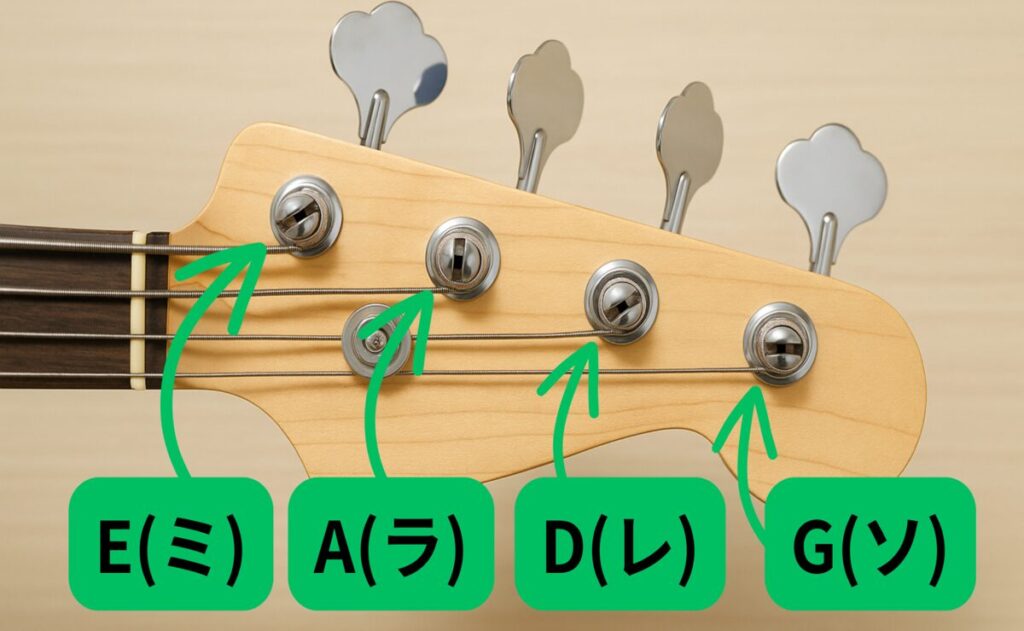
チューニングで改めて音名を確認しましょう。
音名を覚えるのにいい練習になります。
ベースの基本的なチューニングは、
- 4弦 → E(ミ)
- 3弦 → A(ラ)
- 2弦 → D(レ)
- 1弦 → G(ソ)
ここで大事なのは「各弦の音名を意識・理解すること」です。
なんとなく「EADG」って暗記してるだけじゃダメです。
「E=ミ、A=ラ、D=レ、G=ソ」って意識すること。
これ本当に大事。
「E弦、A弦、D弦、G弦」の表記に、
少しずつ慣れていきましょう!
「チューニングってそもそも何?」
「正しいやり方がまだ不安…」
って人は、
チューニングのやり方を解説した記事があるので、
先にそちらを読んでください!👇
エレキベースで音の位置を見て・弾いてみよう

ここからは、
「ベースのどこに、どの音があるのか」
を覚えていきます。
最初から全部を覚えるのは無理です。
「そういえばここの音がCだったな」とか、
「Dはこの辺にあったな」みたいに
なんとな~くでOKです。
ベースを弾いて練習しているうちに、
しっかり頭と体に定着していきます!
エレキベースの指板とフレットの見方を知ろう
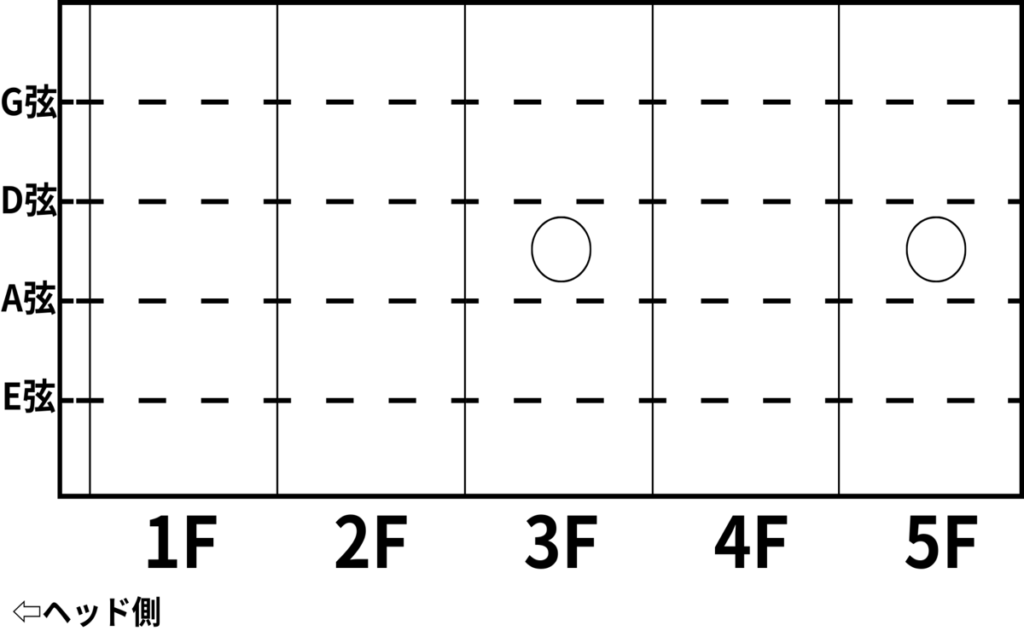
ベース弦を押さえるネックの板みたいな部分を指板と言います。
指板上の、金属の仕切りを「フレット」と呼びます。
フレットとフレットの「間」を押さえることで、
音の高さを調整します。
ヘッド側の一番端の「間」を「1フレット(1F)」
次を「2フレット(2F)」というふうに番号で呼びます。
記事内では「1F・2F」と表記します。
分かりやすくするため、
「5フレット(5F)ごと」に区切って解説します。
Cオクターブを弾いてみよう
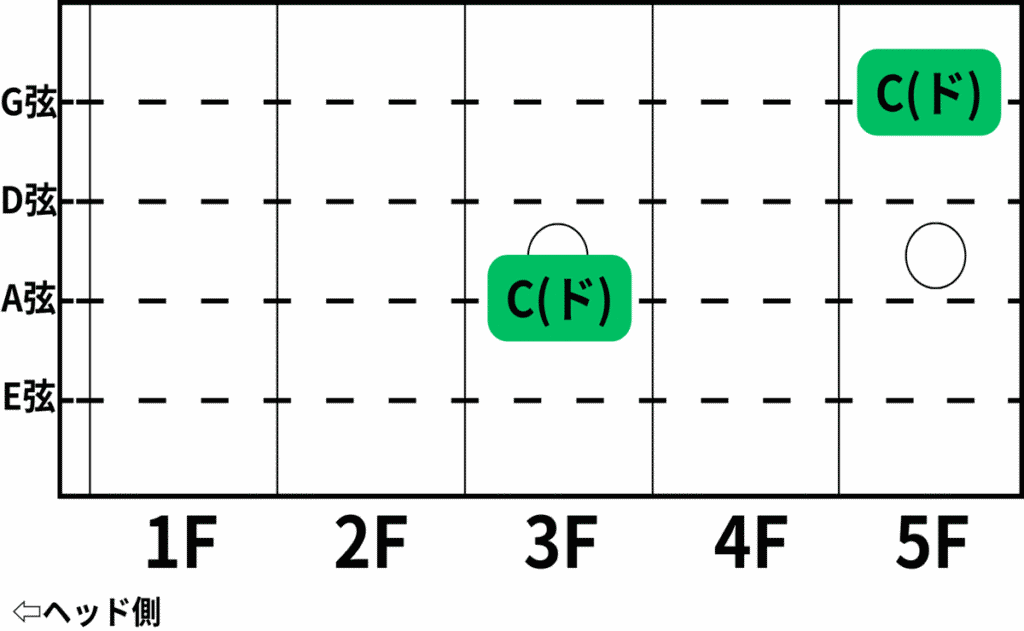
オクターブとは同じ名前の音までの距離のことです。
平たく言えば「ドレミファソラシド」を一周した距離です。
例えば…
- C(低い ド) → C(高い ド)
この「低いC(ド)」と「高いC(ド)」の「間」が1オクターブ。
同じCでも、高い方を「1オクターブ上」
低い方を「1オクターブ下」って表現します。
まずは低いCと高いCを交互に弾いてみましょう!
ベースのオクターブ位置は超シンプル。
どんな音でも、
「1弦またいで2フレット先」にオクターブの上下があります。下図を参考に見てみましょう。
「C」でも「F」でもオクターブは同じ形で存在します。
一見すると難しそうですが、
弾いてみるとめちゃくちゃ簡単ですよ!オクターブ上下を交互に弾いてみてください♪
1~5フレットで「ドレミファソラシド」を弾いてみよう
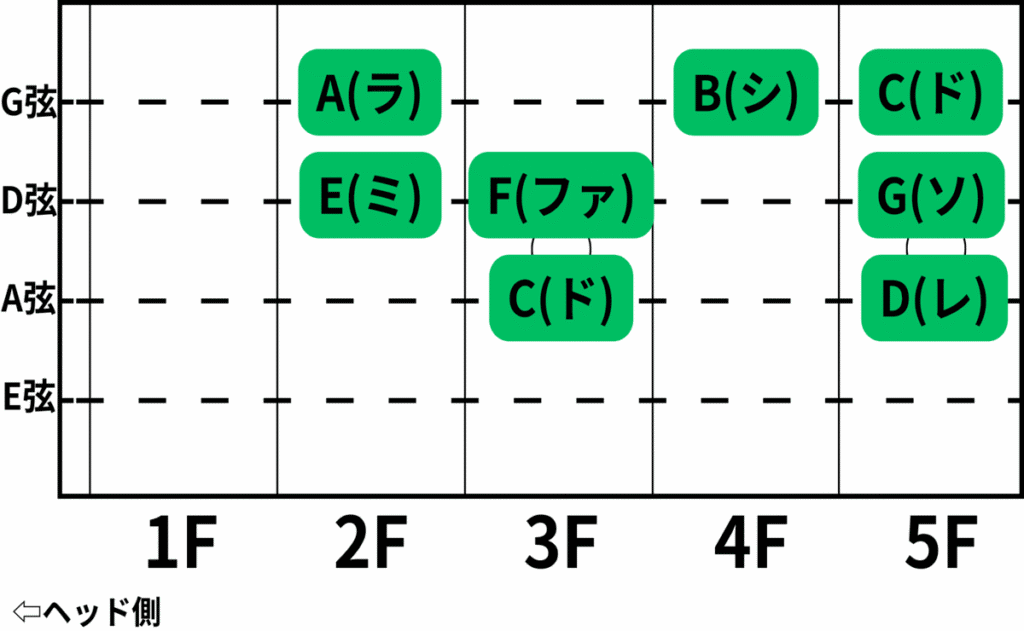
次に1F~5Fまでの、
各音の位置を見ていきましょう。
図では分かりやすいように、
「Cから1オクターブ上のCまでの音」だけ載せています。
実際は、空欄の各フレットに音名がありますが、
今はそこまで気にしなくて大丈夫です。
まずは難しく考えず、弾いてみましょう!
「ドレミファソラシドがこの辺にあるんだな」
って感覚がつかめればOK!
6~10フレットで「ドレミファソラシド」を弾いてみよう
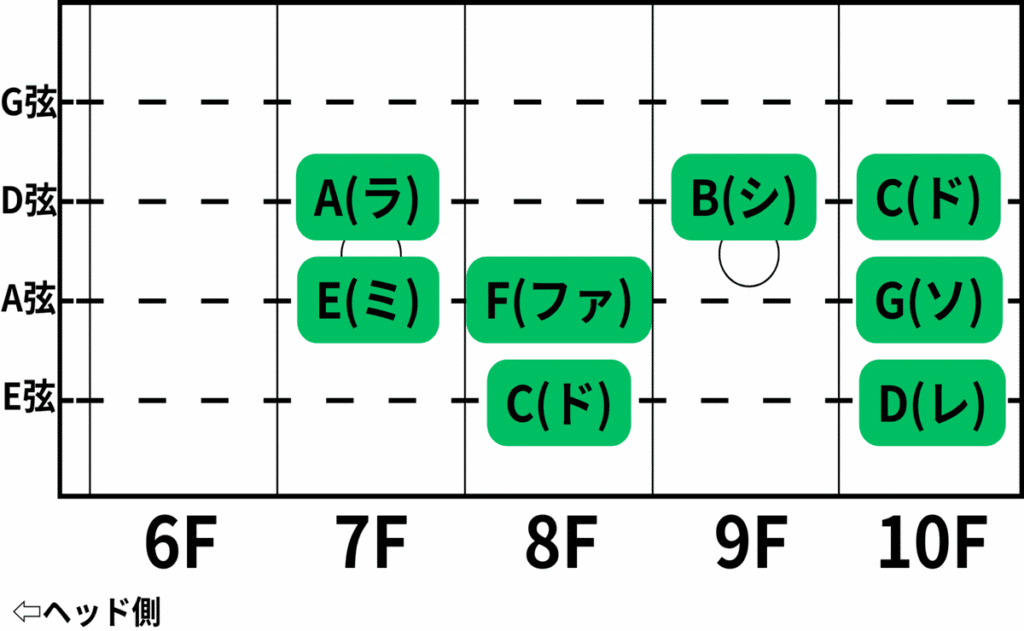
次は6F~10Fを見ていきましょう。
1F~5Fの時と比べると、
Cオクターブの位置が変わりましたね。
けど、よく見てみると…
1F~5Fの「音の並びのブロック」が、
そのままE弦側にスライドしただけなんです!
こうやって見ると、
意外と簡単に弾けそうじゃないですか?
6F~10Fでも同様に、
まずは難しく考えず、弾いてみましょう!
「ここにもドレミファソラシドなのかぁ」
って感覚がつかめればOK!
ちなみにチューナーを付けながら弾くと、
「自分が弾いてる音の音名を目で確認できる」
ので結構感動できておすすめです。
11フレット以降の「ドレミファソラシド」を弾いてみよう
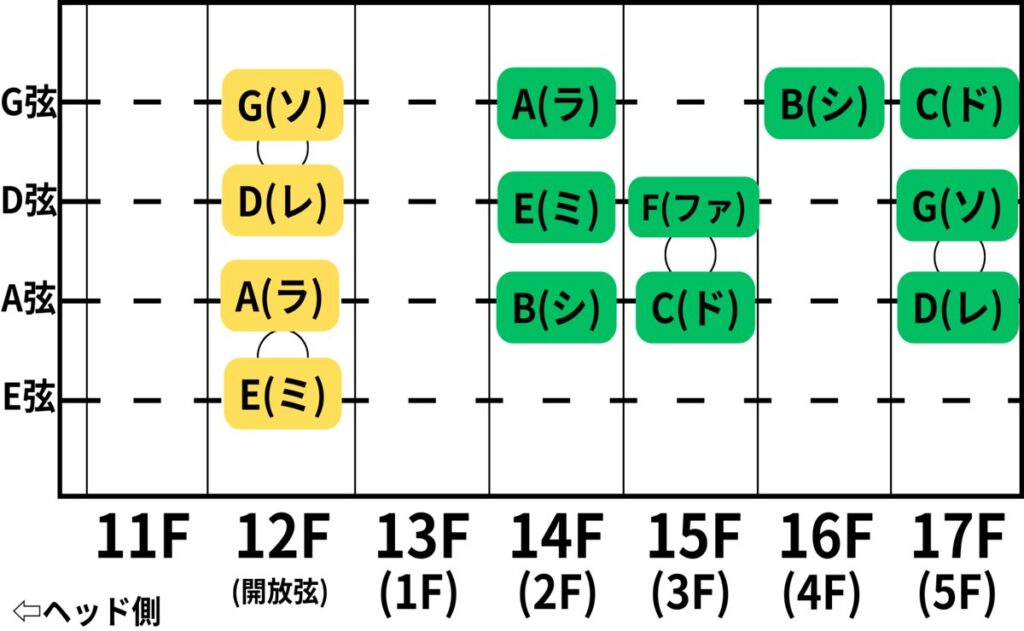
最後に11F以降のポジションはこんな感じです。
「いきなりフレット増やすな!」
って思うかもしれませんが大丈夫です。
ベースは12Fの位置で全ての弦が、
オクターブ(開放弦と同じ音)になります。
なので13F~17Fは、
1F~5Fと同じ音の位置になっています。
18F以降(=6Fから先と同じ並び)は省略します。
18F以降はぜひ、6F~10Fの図を見ながら、
Cのオクターブを自分で探してみてください。
自分で弾きながら探してみると、
「あっ、意外と簡単だな」
って感じると思いますよ!
【音楽理論予備知識】開放弦とは?
「開放弦(かいほうげん)」とは、
フレットを押さえずに弦を弾いた音です。
4弦はE
3弦はA
2弦はD
1弦はG
チューニングした時の音と一緒です。
まとめ 音名は「意識」と「弾いてみる」が大切

今回は音楽理論のスタート地点として、
「音名」について解説してきました。
堅苦しい教科書っぽい内容じゃなく、
「覚えたらすぐ弾ける」くらい実践的な内容になってます。
- 英語音名に慣れよう
- チューニングでも英語音名を意識しよう
- 指板上で音の位置を見て・弾いてみよう
ここまで読んで、
「正直、なんか難しい…」
って感じた人もいるかもしれません。
けど、まずは自分をほめてください。
「音楽理論を学ぼう」と思って、
この記事を読んだあなたは本当に偉い。
音楽理論って、
覚えたらいきなり上手くならないです。
「難しい…」と感じるのも当たり前。
重要なのは、
理解することじゃなく、実践すること。
ある程度理解したら、
理論を意識して何度も演奏することが大事。
音楽理論はあくまで知識です。
けど知識(=基礎)を固めようとする姿勢は、
必ず上達につながります。
次は音と音の距離=「音程」について解説していきます。
一緒にゆっくり進んでいきましょう!
みんな、ベースやろうぜ!

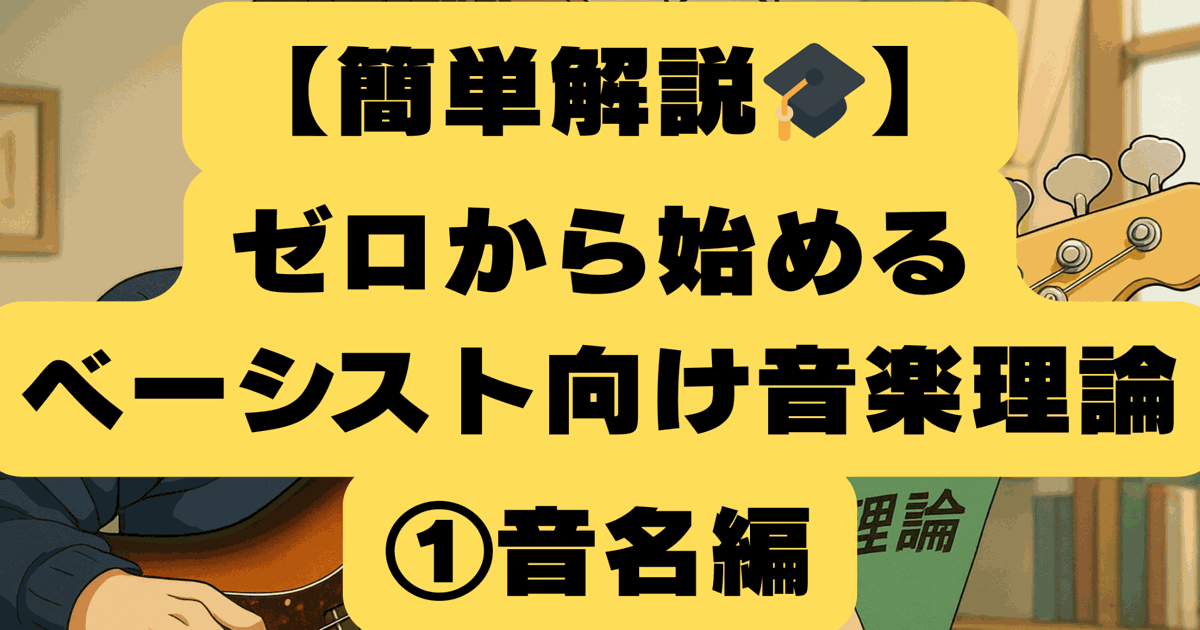
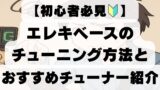
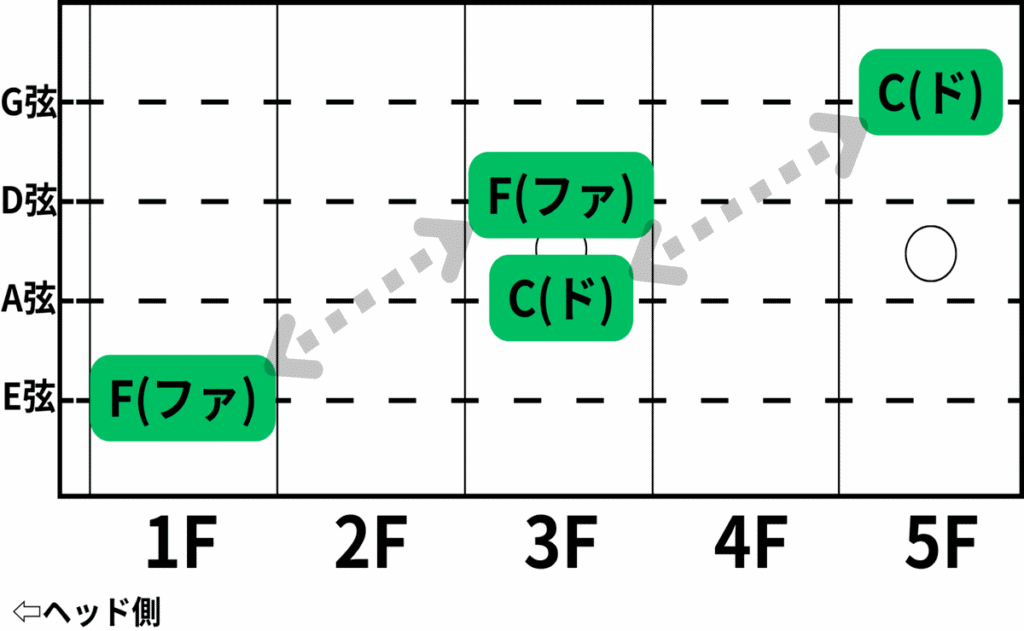

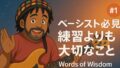
コメント